生命の矛盾と葛藤の美学
若さや美しさに対する追求は、人類が古代から抱える永遠のテーマです。
時が経つにつれて、科学の進歩がこのテーマに新たな洞察をもたらしています。
近年の研究によって大きな関心を集めているのが、「サーチュイン遺伝子」と呼ばれる存在。
人間や他の生き物たちは、通称「若返り遺伝子」と呼ばれるこの遺伝子を保有しています。
この遺伝子は通常、休眠状態にあり、目覚めることはありません。
しかし、飢えや寒さなどの困難な状況に直面したとき、初めて「危機管理レスキュー遺伝子」としてその真価を発揮するのです。
急速に休眠から覚醒し、若返りへの欲望が高まり、身体は元気を取り戻すことになります。
人間の本質的な狩猟本能が再び芽生え、生存をかけた闘争本能が再び息づいていきます。
このメカニズムは、私たちの存在の核心に深く関わっており、生命の矛盾と葛藤の美学がそこに宿るのです。
サーチュイン遺伝子は、まさに内なる「若返りスイッチ」
ウィスコンシン大学の研究において、研究者らが追い求めるのは「サーチュイン遺伝子」の謎解きです。
そこでは、人間に近い存在として知られるアカゲザルたちが主役となります。
エサを自由に食べるグループ(自由摂食)と食事制限を受けるグループに分かれしばらくの間過ごすことに。
その結果、自由にエサを摂取するサルたちは早々に老化し、加齢による病の蔓延を目の当たりにすることとなります。
それに対し、食事制限を受けた仲間たちは、艶やかな毛並みと若々しい輝き、俊敏な動きを保ち、その上、若い頃の脳の機能を取り戻したというのです。
生存率においても、驚く結果が明らかになり、食事制限グループでは約70%が生き残り、一方、エサ自由グループではわずか20%という結果が示されたといいます。
この実験の結果を確かめたければ、ネット上の動画サイトを覗いてみるとよいでしょう。
そこには、サルたちの違いが鮮明に映し出されています。
「サーチュイン遺伝子」は、まさに内なる「若返りスイッチ」なのです。
副作用も特殊な薬も必要なく、そしてお金も必要ありません。
にも関わらず、この発見はスルーされているのです。
まるで「宝の持ち腐れ」と言われるべきではないでしょうか。
目覚めの最短ルート
「サーチュイン遺伝子」の目覚めへの最短ルートは、「飢え」を感じることにあります。
古来より伝わる「腹八分目」という教えが示す通り、一日に一度、食事を摂ることなく空腹を感じることが、長寿の秘訣となるのです。
その反対に、「食べ過ぎは老化の温床」と言えます。
満腹になるまで食事を摂り、小腹が空いた時には軽食を口にし、快適な室温のエアコンの下でのんびり過ごし、運動はほとんど行わず、まったくと言っていいほど「サーチュイン遺伝子」を活性化させていない。
それが「自由摂食」と呼ばれ、この現代社会において広く存在しています。
自由摂食者は、生活の中で常識的な食事制限や運動の必要性を軽視し、快楽と自由を追求する傾向があります。
彼らは罪悪感もなく享楽主義にふけり、生命の本質的な健康とは無縁の存在と言えるでしょう。
一見すると彼らの生活は豊かで満たされているように見えるかもしれませんが、サーチュイン遺伝子の働きの欠如は、細胞の老化を加速させ、病気のリスクを高める可能性があるという科学的な研究結果にもあるのです。
人間の根源的な欲望
過去何百万年もの間、人間は飢えと寒さに強いられていました。
まれにしか得られない獲物。
その存在は生死を分ける、重要な食糧です。
食糧を手に入れても、保存技術の未熟な時代においては一気に味わうことしかできません。
人の肉体は、食糧を効率的にエネルギーに変え、余剰な栄養を皮下脂肪として蓄え、訪れるかもしれない寒さと飢えに備えた、まさに究極の「省エネ体質」へと進化を遂げていきます。
この進化のお陰で、氷河期の試練を乗り越えることが可能となったのです。
以後、比較的安定した食事を享受できるようになったのは、稲作や小麦の栽培が始まってからわずか1万年前のこと。
そして、お腹を満たすことが容易になったのは、せいぜい100年前と言えるでしょう。
食料を手に入れることは単なる食事ではなく、生命力を湛えた儀式のようなものでした。
人類の歴史と共に継承される「サーチュイン遺伝子」の眠りから目覚めようとする衝動。
それは、人間の根源的な欲望の一端を映し出しているのかもしれません。
e-fuel エンタメ クイズ スポーツ センバツ フリースクール ミラクル甲西 ランキング 万博 健康豆知識 凍結防止剤 化学 斎藤知事. 滋賀県 物流2024年問題 生活 甲子園 社会 親子ホームラン 軽油凍結 高校野球

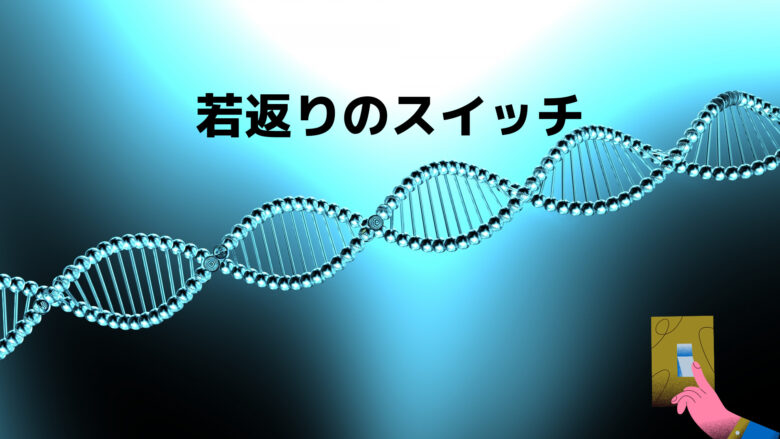
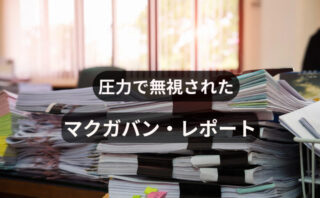






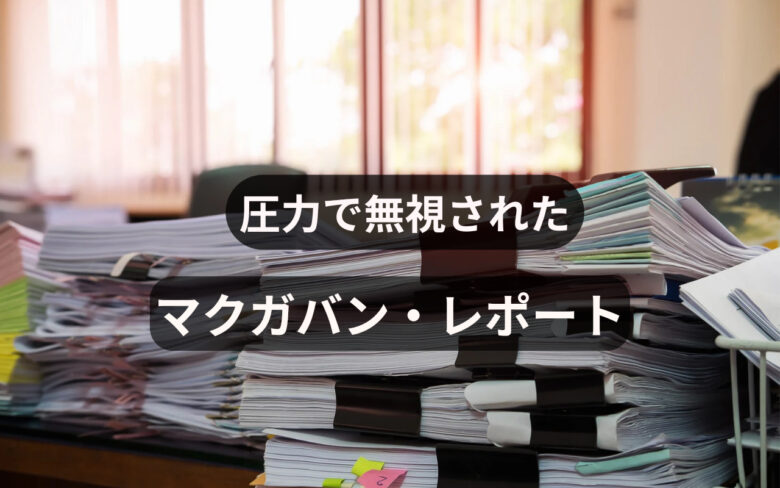
コメント