夏の選手権大会が終わると、甲子園ロスやU-18侍ジャパンロスで寂しい思いをされている方々がたくさんいらっしゃいます。
安心してください。高校野球愛を再び満たす機会は毎年秋に必ず訪れます♪
夏の甲子園で素晴らしい成績を収めた学校の中から、一定の条件を満たした8校だけが選ばれ、高校生活の締めくくりとして臨む「国体高校野球」があるんです。
甲子園のような華やかさはないかもしれませんが、活躍した世代の強豪校が顔を揃える大会ですので特別なお得感があります。
そんな彼らの試合がまた見れる国体って最高です♪
国体高校野球の特徴
夏の選手権大会(地区予選含む)が終わると3年生の引退が決まります。
すぐさま各地区で秋季大会が始まりますので、1.2年生の新チームが始動。
流れは、秋季大会→明治神宮大会→選抜大会(春のセンバツ)→春季大会→
そして新チーム結成からおよそ1年を経て、最後の公式戦である選手権大会(夏の甲子園)を目指すことになります。
この夏の選手権大会で好成績をおさめた高校が「8校」選出され国体に出場できる、という流れになっています。(2022年のとちぎ国体から12校制から8校制に変更されました)
ゆえに国体は、既に1.2年生の新チームが始動している状態で開催されるので、3年生主体で行われています。
夏の甲子園でレギュラーだった下級生は国体ではなく新チームに参加しているケースもあります。これは監督さんの意向によってそれぞれあるようですね。
同日に試合が被らないよう調整されることもありますが、調整できないこともあり、3年生だけで国体へ、下級生だけで監督とともに秋季大会へ臨む日も存在します。
- 1.2年生新チームスタート↓秋季大会(8〜11月)
- 全国を、10地区に分け、各秋季大会を勝ち抜いた10校が集う↓明治神宮大会(11月)
- 秋季大会などの戦いぶりや戦績で全国から32校を選抜、甲子園春のセンバツ大会↓選抜大会(3〜4月)
- 雪や寒さの影響で南の地方から開始されるため開始時期が幅広い。全国大会はない↓春季大会(3〜6月)
- 地方大会優勝校のみ全国大会へ。全国49代表校が出揃いチーム総決算の大会になる↓全国選手権大会(6〜8月)
- 全国選手権大会で一定の条件を満たした8校だけが選出される↓国体(9〜10月)
- 3年生引退 → 1.2年生の新チームスタート。国体と時期が重なる↓秋季大会(8〜11月)
監督さんの意向は過去の試合内容を見てもそれぞれです。選手権大会のように「勝ちに行く」試合もあれば、送りバントもなく自由に打たせる「フリー」な試合も見ることができます。
後者は監督の3年生へのねぎらいを感じられるもので、それはそれとして感慨深いものがあります。
重きを置く部分が各監督さんによって違うため、3大大会(神宮、選抜、選手権)のような鬼気迫るものとは異なり、独特の魅力が溢れています。
国体高校野球の選考基準
先述しましたが、国体に出場できるチームは8校です。
選手権大会でベスト8まで勝ち進んだ高校が出場するのであれば分かりやすいのですが、あまり単純ではないようです。
ではどのような選出方法なのか、2023年夏の選手権大会の成績を振り返って見てみることにしましょう。
以下はベスト16まで勝ち進んだ高校の成績になります。
| 慶應(神奈川) | 優勝(5勝) |
| 仙台育英(宮城) | 準優勝(5勝) |
| 土浦日大(茨城) | ベスト4(4勝) |
| 神村学園(鹿児島) | ベスト4(4勝) |
| 沖縄尚学(沖縄) | ベスト8(補欠校)(2勝) |
| 花巻東(岩手) | ベスト8(3勝) |
| 八戸学院光星(青森) | ベスト8(補欠校)(2勝) |
| おかやま山陽(岡山) | ベスト8(3勝) |
| 北海(北海道) | ベスト16(2勝) |
| 履正社(大阪) | ベスト16(2勝) |
- 創成館(長崎)(1勝)
- 広陵(広島)(1勝)
- 文星芸大付(栃木)(1勝)
- 専大松戸(千葉)(1勝)
- 智弁学園(奈良)(2勝)
- 日大三(西東京)(2勝)
選出条件に明確な基準はありませんが、国体開催地の学校(地元校)とベスト4まで勝ち進んだ学校は確定します。
2023年は鹿児島開催なので、開催地代表の神村学園が、もし甲子園で1回戦敗退をしていたとしても国体に選出されるわけなんです。ただ今回の神村学園は準決勝まで勝ち進んでいるので、ベスト4の成績の枠が1つ余ってきますよね。なので残り4枠を選出する協議となります。
上記を見れば分かりますが、沖縄尚学と八戸学院光星は、ベスト8まで勝ち進んだにも関わらず補欠校。
勝ち星の数でベスト16の学校と同列に見立てられているので、花巻東とおかやま山陽の勝ち星3勝組が選出された形になりました。
このあとはベスト16以上の学校の中から残り2校の枠を協議する形が取られます。
ここから勝ち星1勝組の4校が省かれ、2勝組の6校の中から選出という流れに。
最後は「地域性」を考慮して選出されます。全国の各地方区切りでバランス良く選出されているようです。
2023年の甲子園大会の成績は各地方に偏りがありました。東北や関東、九州勢が活躍する一方で、近畿勢の最高位は履正社と智弁学園のベスト16、中部や北信越、四国勢はベスト16に1校も入っていません。
そのため、沖縄尚学と八戸学院光星の2校が補欠校になり、近畿勢と北海道の学校が選出される形となりました。
地域性の基準は、全国を10地区(北海道、東北、関東、東京、北信越、東海、近畿、中国、四国、九州)に分け考えられています。
- 国体開催地の代表校
- 選手権大会ベスト4以上の成績
- 選手権大会ベスト16以上の中から勝利数や地域性が加味される
国体高校野球(硬式)の歴代優勝校
日本で初めて国体が開催されたのは、戦後まもなくの1946年(昭和21年)。以来現在までの77年、各都道府県が持ち回る形式で続いています。
硬式高校野球も第1回大会から行われています。
| 回 | 年度 | 優勝校 | 都道府県 | 開催地 |
| 1 | 1946年 | 浪華商 | 大阪 | 大阪 |
| 2 | 1947年 | 岐阜商 | 岐阜 | 石川 |
| 3 | 1948年 | 西京商 | 京都 | 福岡 |
| 4 | 1949年 | 静岡城内 | 静岡 | 東京 |
| 5 | 1950年 | 瑞陵 | 愛知 | 愛知 |
| 6 | 1951年 | 広島観音 | 広島 | 広島 |
| 7 | 1952年 | 盛岡商 | 岩手 | 宮城 |
| 8 | 1953年 | 中京商 | 愛知 | 徳島 |
| 9 | 1954年 | 高知商 | 高知 | 北海道 |
| 10 | 1955年 | 四日市 | 三重 | 神奈川 |
| 11 | 1956年 | 高知商 | 高知 | 兵庫 |
| 12 | 1957年 | 坂出商 | 香川 | 静岡 |
| 13 | 1958年 | 作新学院 | 栃木 | 富山 |
| 14 | 1959年 | 日大二 | 東京 | 東京 |
| 15 | 1960年 | 北海 | 北海道 | 熊本 |
| 16 | 1961年 | 中京商 | 愛知 | 秋田 |
| 17 | 1962年 | 西条 | 愛媛 | 岡山 |
| 18 | 1963年 | 下関商 | 山口 | 山口 |
| 19 | 1964年 | 博多工 | 福岡 | 新潟 |
| 20 | 1965年 | 銚子商 | 千葉 | 岐阜 |
| 21 | 1966年 | 松山商 | 愛媛 | 大分 |
| 22 | 1967年 | 大宮 | 埼玉 | 埼玉 |
| 23 | 1968年 | 若狭 | 福井 | 福井 |
| 24 | 1969年 | 静岡商 | 静岡 | 長崎 |
| 25 | 1970年 | PL学園 | 大阪 | 岩手 |
| 26 | 1971年 | 岡山東商 | 岡山 | 和歌山 |
| 27 | 1972年 | 明星 | 大阪 | 鹿児島 |
| 特 | 1973年 | 岩国 | 山口 | 沖縄 |
| 28 | 1973年 | 銚子商 | 千葉 | 千葉 |
| 29 | 1974年 | 土浦日大 | 茨城 | 茨城 |
| 30 | 1975年 | 習志野 | 千葉 | 三重 |
| 31 | 1976年 | PL学園 | 大阪 | 佐賀 |
| 32 | 1977年 | 早稲田実 | 東京 | 青森 |
| 33 | 1978年 | 報徳学園 | 兵庫 | 長野 |
| 34 | 1979年 | 箕島 | 和歌山 | 宮崎 |
| 〃 | 〃 | 都城 | 宮崎 | |
| 〃 | 〃 | 浪商 | 大阪 | |
| 〃 | 〃 | 浜田 | 島根 | |
| ※4校優勝 | 雨天打切り | |||
| 35 | 1980年 | 横浜 | 神奈川 | 栃木 |
| 36 | 1981年 | 今治西 | 愛媛 | 滋賀 |
| 37 | 1982年 | 広島商 | 広島 | 島根 |
| 38 | 1983年 | 中京 | 愛知 | 群馬 |
| 39 | 1984年 | 取手二 | 茨城 | 奈良 |
| 40 | 1985年 | 高知商 | 高知 | 鳥取 |
| 41 | 1986年 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 山梨 |
| 42 | 1987年 | 帝京 | 東京 | 沖縄 |
| 43 | 1988年 | 沖縄水産 | 沖縄 | 京都 |
| 44 | 1989年 | 上宮 | 大阪 | 北海道 |
| 45 | 1990年 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 福岡 |
| 46 | 1991年 | 松商学園 | 長野 | 石川 |
| 47 | 1992年 | 星稜 | 石川 | 山形 |
| 48 | 1993年 | 修徳 | 東京 | 香川 |
| 49 | 1994年 | 北海 | 北海道 | 愛知 |
| 50 | 1995年 | PL学園 | 大阪 | 福島 |
| 51 | 1996年 | PL学園 | 大阪 | 広島 |
| 52 | 1997年 | 徳島商 | 徳島 | 大阪 |
| 53 | 1998年 | 横浜 | 神奈川 | 神奈川 |
| 54 | 1999年 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 熊本 |
| 55 | 2000年 | 横浜 | 神奈川 | 富山 |
| 56 | 2001年 | 横浜 | 神奈川 | 宮城 |
| 57 | 2002年 | 川之江 | 愛媛 | 高知 |
| 58 | 2003年 | 光星学院 | 青森 | 静岡 |
| 59 | 2004年 | 横浜 | 神奈川 | 埼玉 |
| 60 | 2005年 | 駒大苫小牧 | 北海道 | 岡山 |
| 61 | 2006年 | 早稲田実 | 東京 | 兵庫 |
| 62 | 2007年 | 今治西 | 愛媛 | 秋田 |
| 63 | 2008年 | 優勝校なし | 台風打切り | 大分 |
| 64 | 2009年 | 県岐阜商 | 岐阜 | 新潟 |
| 65 | 2010年 | 優勝校なし | 雨天打切り | 千葉 |
| 66 | 2011年 | 日大三 | 東京 | 山口 |
| 67 | 2012年 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 岐阜 |
| 〃 | 〃 | 仙台育英 | 宮城 | |
| ※両校優勝 | 台風決勝無し | |||
| 68 | 2013年 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 東京 |
| 〃 | 〃 | 修徳 | 東京 | |
| ※両校優勝 | 同点延長無し | |||
| 69 | 2014年 | 明徳義塾 | 高知 | 長崎 |
| 70 | 2015年 | 東海大相模 | 神奈川 | 和歌山 |
| 71 | 2016年 | 履正社 | 大阪 | 岩手 |
| 72 | 2017年 | 広陵 | 広島 | 愛媛 |
| 73 | 2018年 | 浦和学院 | 埼玉 | 福井 |
| 〃 | 〃 | 金足農 | 秋田 | |
| 〃 | 〃 | 大阪桐蔭 | 大阪 | |
| 〃 | 〃 | 近江 | 滋賀 | |
| ※4校優勝 | 台風打切り | |||
| 74 | 2019年 | 関東一 | 東京 | 茨城 |
| 75 | 2020年 | 中止 | 新型コロナ影響 | 鹿児島 |
| 76 | 2021年 | 中止 | 新型コロナ影響 | 三重 |
| 77 | 2022年 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 栃木 |
| 10月11日 | 追記↓ | |||
| 特 | 2023年 | 仙台育英 | 宮城 | 鹿児島 |
| 〃 | 〃 | 土浦日大 | 茨城 | |
| ※両校優勝 | 雨天打切り |
各地区別で優勝回数を見ると、関東勢が22回で近畿勢が17回、以下は四国11回、中部9回,中国5回、九州4回、東北4回、北海道3回、北信越2回となっています。
都道府県別で見ると、大阪府が13回、東京都が8回,神奈川県6回優勝しています。
学校別では、横浜高校が5回,PL学園が4回、大阪桐蔭が4回となっています。
赤い太字の学校は春夏連覇し、最後の国体でも優勝しています。
過去に4回記録されていますが、1998年の横浜高校だけは天候による打切りなどがなく、実際に決勝まで試合が行われて優勝を果たしています。元プロ野球選手の松坂大輔さんの時代ですね。
この世代の横浜高校は、公式戦44連勝のまま引退という驚異的な強さを誇っています。選手権大会の準々決勝以降の試合は今思い返しても全てが神がかり的。
国体では主に抑えにまわっていた松阪投手ですが、それでも優勝してしまうところに選手層の厚さを感じました。
まとめ
国体高校野球は、3年生選手にとって最後の舞台です。
大学や社会人、プロで野球を続けたいと考える選手にとってはアピールできる最後のチャンスでもあります。
ほんの2ヶ月前に夏の甲子園の終盤で力を見せあった仲、また高校日本代表のチームメイ卜として絆を深め合った仲間の再会もあります。
試合もさることながら、選手たちの表情にも注目してみましょう♪
━━ということで今回は、国体高校野球の特徴や選考基準、また歴代優勝校についてまとめました。
さいごに
入部から2年半にわたる苦難を共に乗り越え、仲間との絆を深めながら歩んできた選手たちにとって、この大会は高校野球への熱い思いと別れの感情が交錯する場として特別な思い出となる大会であるはずです。
そして、これから彼らの野球人生は新たなステージへ向かうことになります。この大会が、彼らの未来への勇気と希望の礎となり、永遠に心に残る瞬間として刻まれることを願っています。




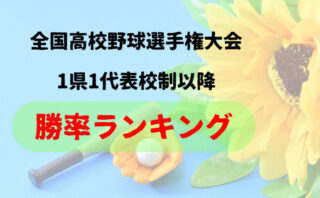

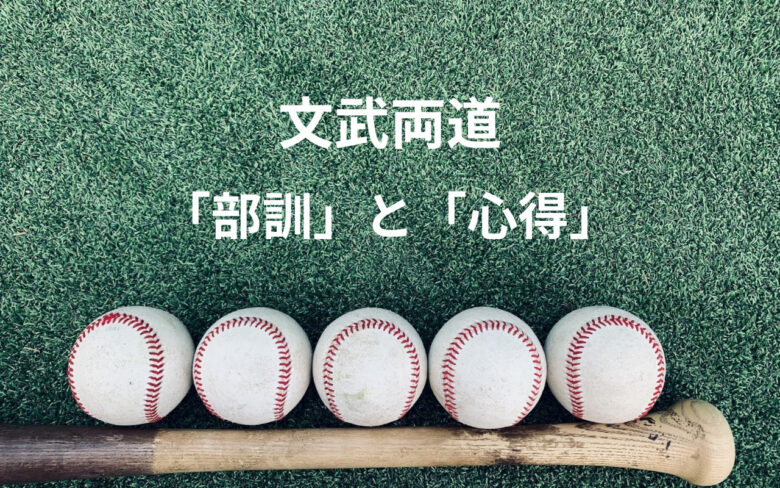

コメント